§2.サブポアソン光発生のポアソン過程による記述の妥当性に関する実験的検討
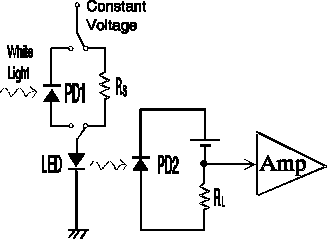
サブポアソン光の発生機構及び高次の揺らぎの研究
平野琢也、篠崎元、安部淳一、久我隆弘
東大 教養 相関基礎(物理) 〒153 目黒区駒場3-8-1
発光ダイオードによるサブポアソン光の発生のメカニズムに関して、以下の3点について報告する。(1)素子の平均効率と微分効率が異なる場合のファノ因子の測定結果。(2)素子のI-V特性と効率の関係。(3)オシロスコープを用いたサブポアソン光の光子数分布関数の測定。
§1. はじめに
半導体発光素子は、注入する電流の揺らぎを小さくすることにより、非古典光(サブポアソン光)を比較的容易に発生することができる。非線形光学効果による非古典光の発生に比べると、実験装置が簡便である、エネルギー効率が良い、デバイスの構造や電子系を変化させることによるシステムの制御性が良い等の利点がある。
しかし、この分野の研究の現状は、サブポアソン光の発生を記述する量子力学的な理論の未整備、光子数スクイージング以外のサブポアソン光の性質が未解明である、スクイージングの周波数帯域が広く強度が微弱なサブポアソン光を発生するのが困難であるといった多くの課題が残されている。本研究は、実験的な研究を通して、これらの課題に取り組んでいる。
§2.サブポアソン光発生のポアソン過程による記述の妥当性に関する実験的検討
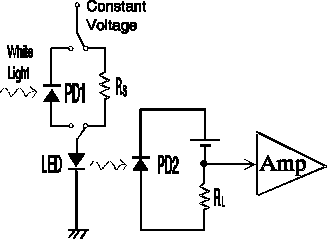
数の揺らぎの大きさは、ポアソン分布の場合の大きさで規格化した、ファノ因子と呼ばれる量を用いると便利である。ポアソン分布の標準偏差は平均値に等しいので、ファノ因子Wは、W=<d n
2>/<n>で与えられる。半導体発光素子に注入する電子のファノ因子をWELとし、発光過程をポアソン過程として扱うと、発生する光子のファノ因子WPHは次式で与えられる[1,2]。
WPH=1-h +h WEL (1)
ここで、h は発光効率であり、この場合、微分効率が平均効率と異なるといった状況は考慮されていない。(1)式によれば、
WEL=0の時、WPH=1-h となり、発光効率の大きさだけ量子雑音限界よりも小さな揺らぎを持つ、サブポアソン光を発生することができる。一方、WEL=1の時は、WPH=1となり、発光効率の値に依らず、ポアソン光が発生する。実験では、
WEL=1のポアソンモードの時の雑音レベルの大きさで、WEL=0のサブポアソンモード時の雑音レベルを規格化する。実験配置図を図1に示す。ポアソンモードの時は、電球又は発光効率の比較的低いLEDからの光で照射したフォトダイオードを通した電流を用いる。サブポアソンモード時は、定電圧源を高抵抗に通すことにより、WEL» 0を実現する。この規格化の方法は、実験配置の変更を最小限にして、雑音レベルを規格化することができるので、多くの実験で用いられている。
図2に、スペクトラムアナライザ(SA)で観測した雑音スペクトルを示す。測定系は常にそれ自身の雑音を持っており、特に、増幅器の入力インピーダンスで発生する熱雑音は原理的に必ず存在する。そのため、SAで観測される雑音は、光電流の雑音と測定系の持つ雑音との和になる。そこで、ファノ因子を求めようとするときは、二つの雑音に相関がないことを利用して、測定系の雑音を引き算する。
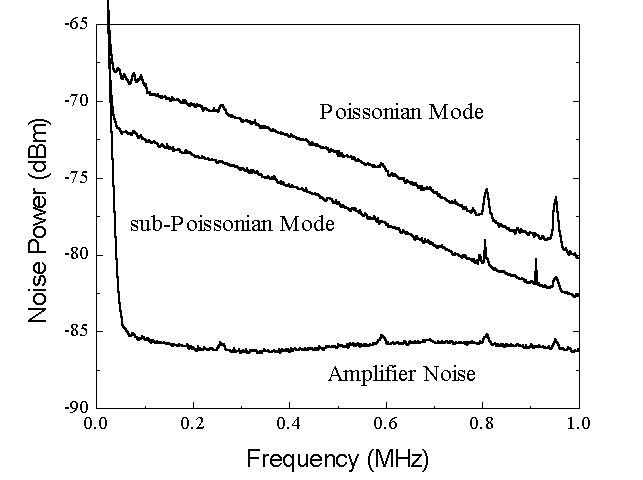
図3に、上述の熱雑音の補正を施した後、サブポアソンモードの雑音を、ポアソンモードの雑音で規格化した雑音レベルを示す。3つのデータは、LEDへの注入電流が異なる時のもので、それぞれフォトダイオード(PD)で受光した電流値が、500m A、50m A、5m Aである。使用したLEDは、日立製HLP40RDで、動作させた温度は室温である。このLEDの遮断周波数は、100MHzであるので、観測周波数の1MHzの中で、ほぼ一様なスクイージングが実現されている。このようなフラットな特性は、規格化した雑音レベルの大きさを評価し易いというメリットがある。
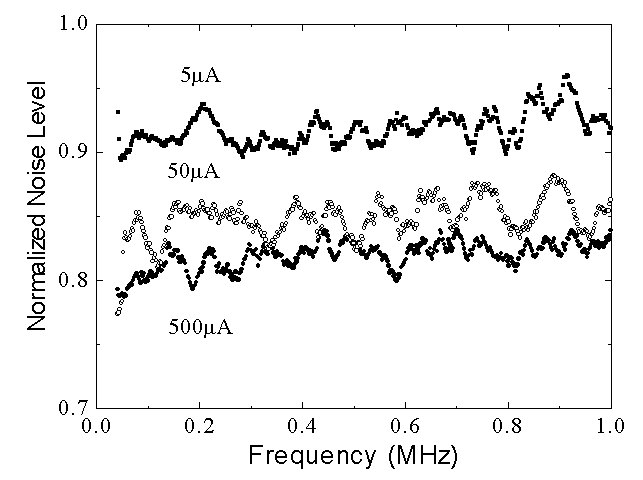
表1に、規格化した雑音レベルの大きさと、それぞれの注入電流値での平均発光効率から予測される計算値を示した。(1)式によれば、規格化した雑音レベルの大きさは、1-(効率)で与えられるはずであるが、測定値はそれよりも小さくなっている。つまり、実験で測定される規格化した雑音の大きさは、単純なポアソン過程による理論とは定量的に一致しない。この実験では、素子の平均発光効率と微分発光効率が異なっているので、その効果について考慮してみる。
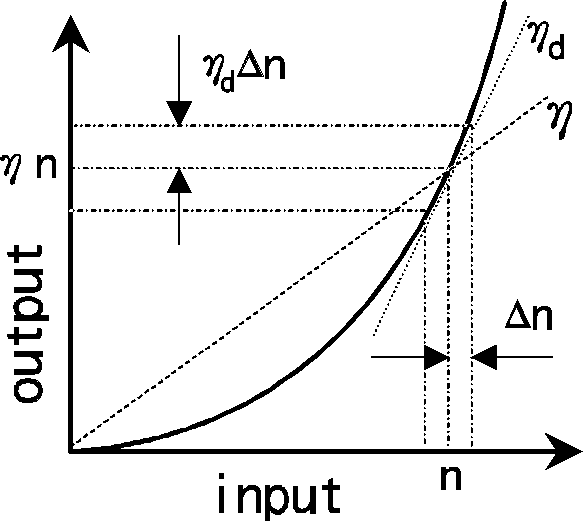
|
IPD |
Exp. |
1- η |
? 1-h ???1-h ?h d2/h ? |
||
|
5m A |
0.90 |
0.93 |
0.89 |
||
|
50m A |
0.84 |
0.89 |
0.85 |
||
|
500m A |
0.81 |
0.85 |
0.80 |
||
電子や光子を粒子として捉える描像では、微分効率の役割を考えるのは難しいので、図4のような小信号伝達的な描像で、微分効率の直観的な意味を考える。図の横軸は入力電流を、縦軸は出力を表している。入出力特性が図のような曲線で表される場合、原点から引いた直線の傾きで表される平均効率は、接線の傾きである微分効率よりも小さくなる。入力電流の平均値が
nの時、平均出力はh nである。入力がD n変動するとき、出力側の変動は、h dD nである。この時、出力のファノ因子Woutは、Wout =(h dD n)2/(h n) =h d2/h ?D n)2/n =h d2/h WINとなるが、ランダムな損失による揺らぎの付加を考慮すると次式が得られる[3]。Wout=1-h
?h d2/h WIN (2)(2)式によると、
WEL=1に対してWPH=1-h ?h d2/h となる。これは、h d?h の時、WPH??とスーパーポアソン分布となる。この場合、規格化した雑音レベルは、?1-h ???1-h ?h d2/h ?になると予想されるが、表1を見ると、実験値と良く一致している。
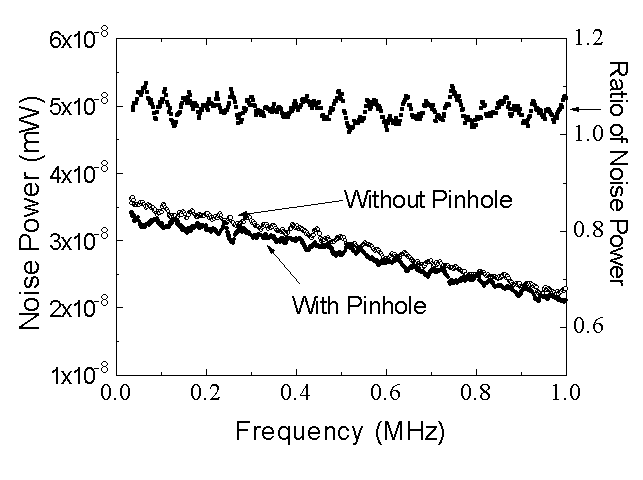 もっと直接的に、スーパーポアソン化するかどうかを調べるために、ピンホールを用いて、
もっと直接的に、スーパーポアソン化するかどうかを調べるために、ピンホールを用いて、
§3. トラップ準位を考慮した発光効率の定量的なモデル
LEDの発光効率は、注入電流の大きさにより変化する。この現象は、トラップ準位の存在を仮定し、有限の個数のトラップ準位が飽和を起こすことにより、定性的に理解できることを以前報告していた。しかし、トラップ準位の飽和のみを考慮したレート方程式による定量的なモデルでは、実験で得られる入出力特性を再現することができなかった。この章では、より現実的なモデルにより、LEDの発光効率や発光過程についての理解を深めることを目的とする。
一般に、順電圧をかけた半導体中を流れる電流は、拡散電流と再結合電流(Generation-recombination current)の和として表すことができる[4]。
J=JS exp(eV/kT)+JR exp(eV/2kT) (3)
再結合電流は、トラップ準位による電子捕獲や正孔捕獲、あるいは逆のプロセスにより起こる。この二つの電流の接合電圧
V依存性は、指数関数の係数が2倍異なっている。このため、Vの小さな時は、再結合電流が支配的であっても、Vが大きくなるに従って拡散電流が支配的となる。発光に寄与するのは、拡散電流なので、次式で定義される注入効率を考える[5]。h inj= JS exp(eV/kT) / J (4)
接合電流が光に変換される効率、発光した光が外部に出る効率等が注入電流に依存しない場合は、(4)式の注入効率により、実験結果が説明できると期待される。上述したように、注入電流が小さいときは再結合電流が支配的になるので、注入効率は小さくなる。逆に、接合電流が支配的になる領域では、注入効率は1に近づく。
図6に、日立製HE8403SGの接合電圧−電流の室温での測定結果を示す。順電圧が大きくなるに従って、グラフの傾きが大きくなっている。(3)式に、素電荷e、ボルツマン定数k、温度Tの値を代入し、J
SとJRをフィッティングパラメータとして、フィッティングを行って得られた結果を、図6の実線で示した。(3)式により実験結果をよく説明できることが分かる。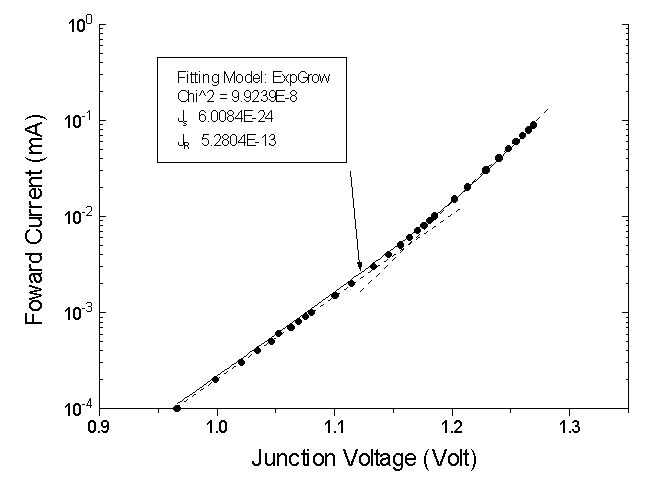
J
SとJRが得られれば、(4)式により注入効率を計算することができる。図7にその結果を示す。黒丸は実測した効率、+印が計算結果である。両者を合わせるために、計算結果には、LEDからPDへの結合効率を考慮し、比例定数0.21を掛けた。両者を比べると良く一致していることが分かる。微分効率も、同様に、実測値を計算で再現できた。このことは、発光効率の注入電流依存性を、注入効率により説明できることを示している。つまり、トラップ準位を介した再結合過程が、発光効率のメカニズムで重要な役割を果たしていることが分かった。今後、文献[3]の計算で用いられた寿命のキャリア濃度依存性を考えるモデルとの関係について、理解を深めていきたい。(4)式によれば、J
SとJRの比という一つの定数が分かれば、あらゆる温度での効率を予測できることになる。しかし、残念ながら、液体窒素温度での実験結果とは一致しないことが分かった。今後、中間温度での測定を行うことが必要であろう。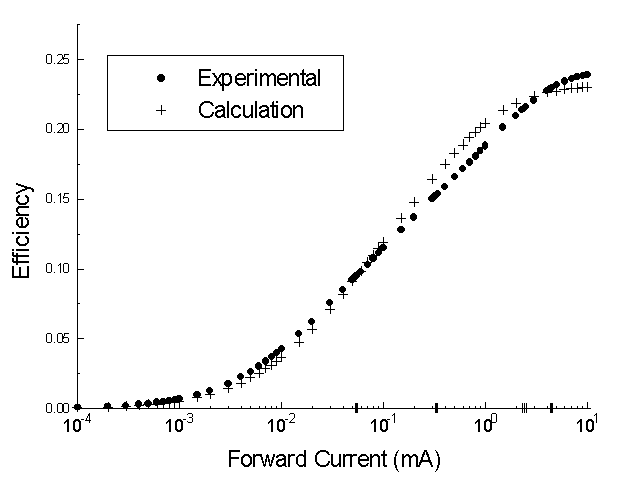
§4. 光子数分布関数の測定
これまでに実験で調べられているサブポアソン光の性質は、ファノ因子の測定、つまり、光子数の揺らぎ(分散)を調べたものがほとんどである。閉じた系の中でフィードバックを掛けたLDで発生させたサブポアソン光の光子数分布関数を測定した実験はあるが[6]、定電流駆動の場合の実験はない。光子数分布関数は、その幅のみよりも、はるかに多くの情報を含むので、サブポアソン光の性質に関して新たな知見の得られる可能性がある。特に、周波数軸上でファノ因子が悪化する時間領域や、微分効率の効果によりスーパーポアソン化する場合に、興味深い結果が得られるかもしれない。この章では、現在我々が行っている光子数分布関数の測定の現状について述べる。
実際の実験は、図1の配置図のアンプの後ろにデジタルオシロスコープ(Lecroy 9310AM)を接続して行う。このオシロは、最高10Gsで250kワードのメモリを持っており、縦軸の分解能は8bitである。このようにして得られる時間波形を、パソコンを使ってフーリエ変換して得たパワースペクトルを図8に示す。この時の出力の光電流は1mAで、サンプリング時間は40nsである。図8は、図2に相当するもので、同様な結果が得られている。
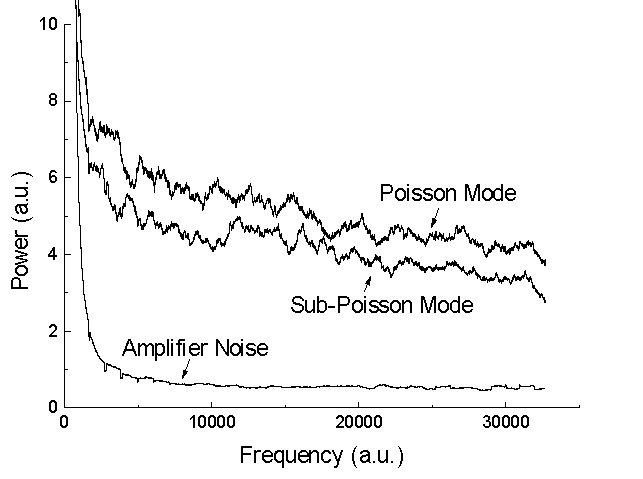
図8を見ると分かるように、測定した時間波形は、測定系の雑音も含んでいるので、これを取り除くことにする。そのために、フーリエ変換したデータに、最適化フィルター(Wienerフィルター)を施して逆フーリエ変換を行った。Wienerフィルタ、W(f)=S(f)/(S(f)+N(f))は、図8のデータより求めた。S(f)、N(f)は、それぞれ、信号及び雑音のパワースペクトルである。
このようにして測定系の雑音を取り除いた時間波形の波高値を、ヒストグラムにした結果を図9に示す。横軸はオシロスコープで測定される電圧で、光電子数の平均値からのずれを表している。この図の平均個数は2.5x108個、横軸は2.5x106個/Vと見積もられる。図9は、光電流の分布関数そのもので、光子数分布関数とはPDの損失による畳み込み分異なる。図のポアソンモード、サブポアソンモードいずれの場合も、関数はガウシアンと非常に良く一致している。また、サブポアソンモードの幅は、ポアソンの時より細くなっている。その分散の比は、(1.64/1.87)^2=0.77と、効率21%から期待される値とほぼ一致する。
§5. まとめ
微分発光効率が平均効率よりも大きい時、注入する電流がポアソン分布で与えられる揺らぎを持っていても、発生した光子はスーパーポアソン的な揺らぎを持つことを示した。また、得られた規格化した雑音の大きさは、藤崎・清水による理論式とよい一致を示した。これらの結果は、単純なポアソン過程による描像が不十分であることを示している。
発光効率のポンプレート依存性を定量的に与えるモデルを示した。実測した接合電圧と電流の関係から得られるパラメータにより、少なくとも室温においては、平均発光効率および微分発光効率の注入電流依存性を定量的に説明することができた。
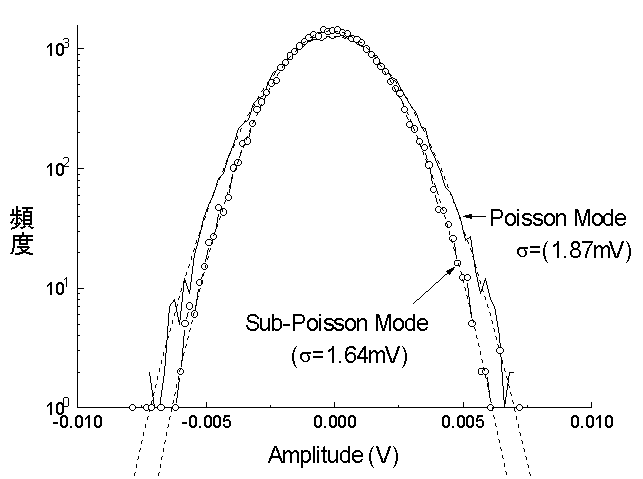
定電流駆動された半導体発光素子から発生したサブポアソン光の光子数分布関数を初めて測定した。
参考文献
[1] M.C. Teich and B.E.A. Saleh, Opt. Lett. 7, 365 (1982).
[2]
清水明, 応用物理学会誌, 第62巻, 第9号, p.881-888, (1993).[3] Hiroshi Fujisaki and Akira Shimizu, CLEO/Pacific Rim’95, PD1.7.
[4] David Wood, Optoelectronic Semiconductor Devices, Prentice-Hall International, 1994.
[5] Tadashi Saitou and Shigekazu Minagawa, JJAP, 15, 855 (1976).
[6] Y. Yamamoto, N. Imoto, S.Machida, Phys. Rev. A33, 3243 (1986).